
INDEX
はじめに|今、注目される「やり抜く力」
教育の現場やビジネスの世界で近年よく耳にするようになった言葉に「GRIT(グリット)」があります。日本では「やり抜く力」と訳され、いわゆる学力やIQとは異なる「非認知能力」の一種として、世界的にも注目を集めている概念です。GRIT(グリット)は、学力テストの点数や学歴では測りきれないけれど、人生の成功や社会的な達成に大きな影響を与える力であるとして、教育関係者や保護者の間でも関心が高まりつつあります。
本記事では、GRIT(グリット)とは何か、その基本的な定義や構成要素、そして、GRIT(グリット)は子どもにとってなぜ大切な力なのかを、わかりやすく整理していきます。さらに、GRIT(グリット)と非認知能力との関係性について、最新の研究を参考にしながらご紹介します。
GRIT(グリット)とは?|非認知能力との関係

GRIT(グリット)とは、「やり抜く力」という意味の言葉で、ペンシルベニア大学心理学教授で心理学者アンジェラ・リー・ダックワース氏が提唱しました。GRIT(グリット)は「困難や失敗に直面してもあきらめず、目標を達成するまで粘り強く努力し続ける力」とされており、以下の2つの要素から構成されています。
- 情熱(Passion):ある目標に対して長期にわたり一貫した興味や関心を持ち続ける力
- 粘り強さ(Perseverance):障害に直面してもくじけず、諦めずに努力を続ける力
ダックワース氏は、大きな成功を収めた人々に共通するのは、IQや才能ではなく、「情熱」と「粘り強さ」をあわせ持つこと、すなわち「GRIT(やり抜く力)」が強いことであると述べています。
またGRITは、従来の学力テストで測られるようなIQや知識量とは異なり、「非認知能力」として分類されます。非認知能力とは、自己制御やコミュニケーション能力、協調性、自己肯定感、好奇心といった、人間が社会で生きていくために不可欠な内面的な力です。
GRITが子どもに与える影響|学力や非認知能力との関係

GRITが子どもの成長や将来にどのような影響を与えるのかについては、国内外で数多くの研究が行われており、その有効性が明らかになってきています。以下に、代表的な研究結果とその意義について紹介します。
1. GRITは成功や学力の土台になる
アメリカ・ウェストポイント士官学校での研究では、厳しい訓練を最後までやり遂げられるかどうかを予測する上で、学力テストや体力テストよりも「GRIT」のスコアが最も強い指標であることが明らかになりました。つまり、成功するためには、頭の良さよりも「やり抜く力」が重要である可能性が高いということです。
また、日本でも類似した結果が得られています。横浜市教育委員会と横浜国立大学が2023年に実施した共同研究では、GRITのスコアが高い児童ほど、国語や算数といった主要教科の学力テストにおいて高い成績の伸びを示す傾向が見られました。これは、GRITが学力の“土台”を支えている力であることを示唆しています。
2. GRITは非認知能力と深くつながっている
GRITは単体の能力ではなく、「自己統制力」「モチベーションを維持する力」「主体性」「自己管理能力」など、複数の非認知能力の統合的な成果と捉えることができます。2021年に岐阜大学の杉浦氏らが行った研究では、幼児におけるGRIT的特性(特に忍耐力)が知能指数(IQ)と有意に相関していることが報告されています。この結果は、GRITが単なる「やる気」ではなく、認知能力との関係性も持ち合わせていることを示しており、将来的な学力や社会的成功の予測因子としても注目されています。
3. GRITは遊びや日常の体験から育まれる
同研究では、子どもたちが日々の生活や遊びを通してGRITを養っていることにも注目しています。運動遊びやグループ活動、挑戦的な体験を通じて、子どもは物事に粘り強く取り組む姿勢を身につけると報告されています。
また、横浜市の調査では、「授業が楽しい」と感じている児童や、熱意ある教師と関わる機会が多い児童ほど、GRITやソーシャルスキルが高い傾向にあることも示されています。これは、GRITの育成には環境的な要因、特に教育者の姿勢やクラスの雰囲気が大きく影響することを意味しています。
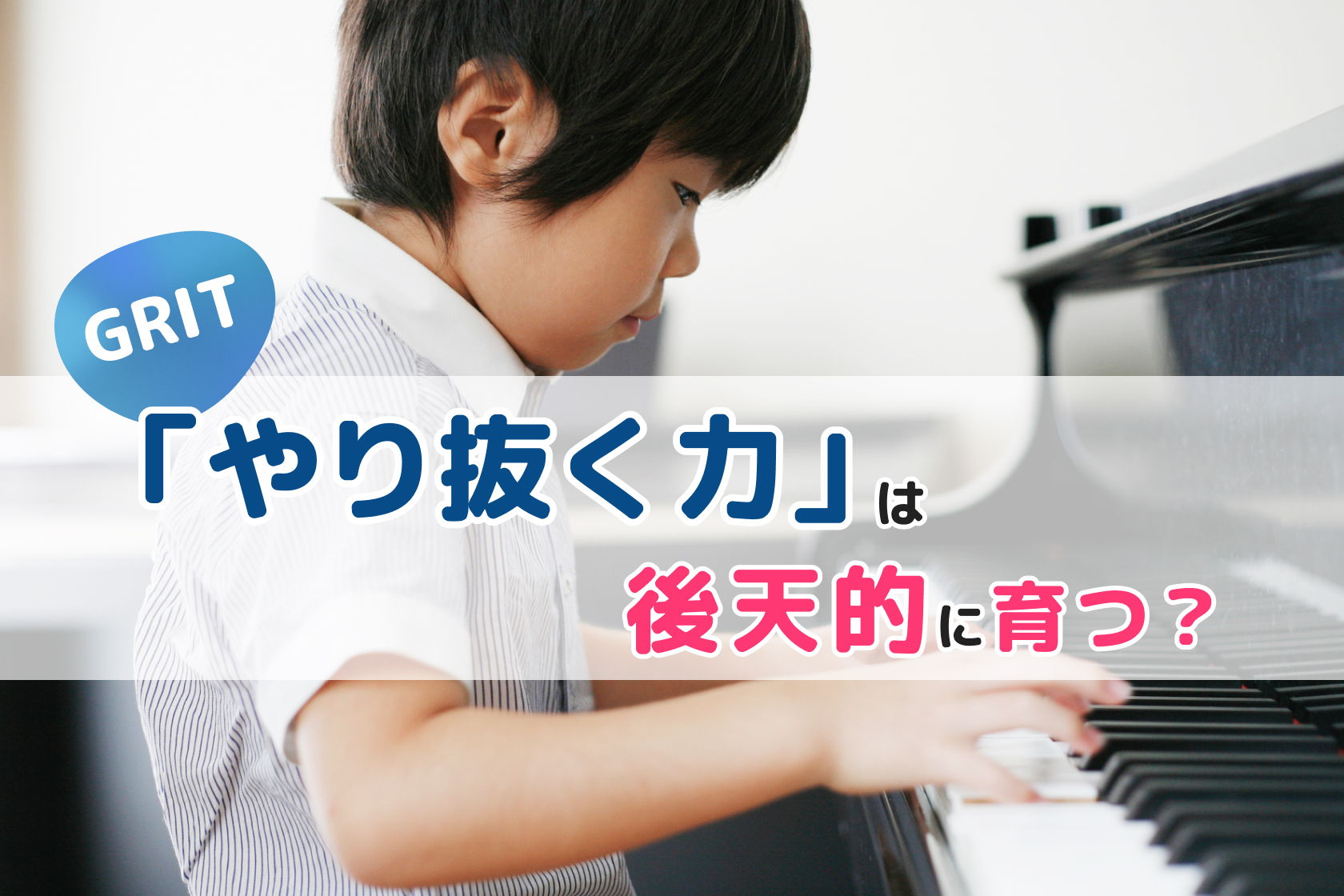
まとめ|やり抜く力は未来を切り拓く武器になる

GRITは、これからの時代を生きる子どもたちにとって、学力や知識と並ぶ重要な「生きる力」のひとつです。単に結果を出すための能力ではなく、困難に対して立ち向かい、自分の目標に向かって着実に努力を積み重ねる力は、社会的にも精神的にも大きな武器となるでしょう。
そして、GRITは非認知能力と連動して、認知能力の成長を土台から支えていることが多くの研究から明らかになっています。これまで「見えにくい」とされてきた非認知能力ですが、今ではその重要性が認識され、教育現場や家庭でも注目されるようになっています。
学力テストでは測れない「隠れた才能」を見つけ、子どもの可能性を引き出す第一歩として、GRITを含む非認知能力の育成に、ぜひ目を向けてみてください。
参考文献・引用元
- 横浜市教育委員会「認知・非認知能力調査研究報告書概要版」(2023年)
- 一般財団法人日本生涯学習総合研究所「非認知能力の概念に関する考察<集約版>」(2022年)
- 杉浦ひなのほか(2021年)『幼児の認知能力と非認知特性の関連』
- アンジェラ・ダックワース (著), 神崎 朗子 (翻訳)(2016年)『やり抜く力 GRIT(グリット)』



