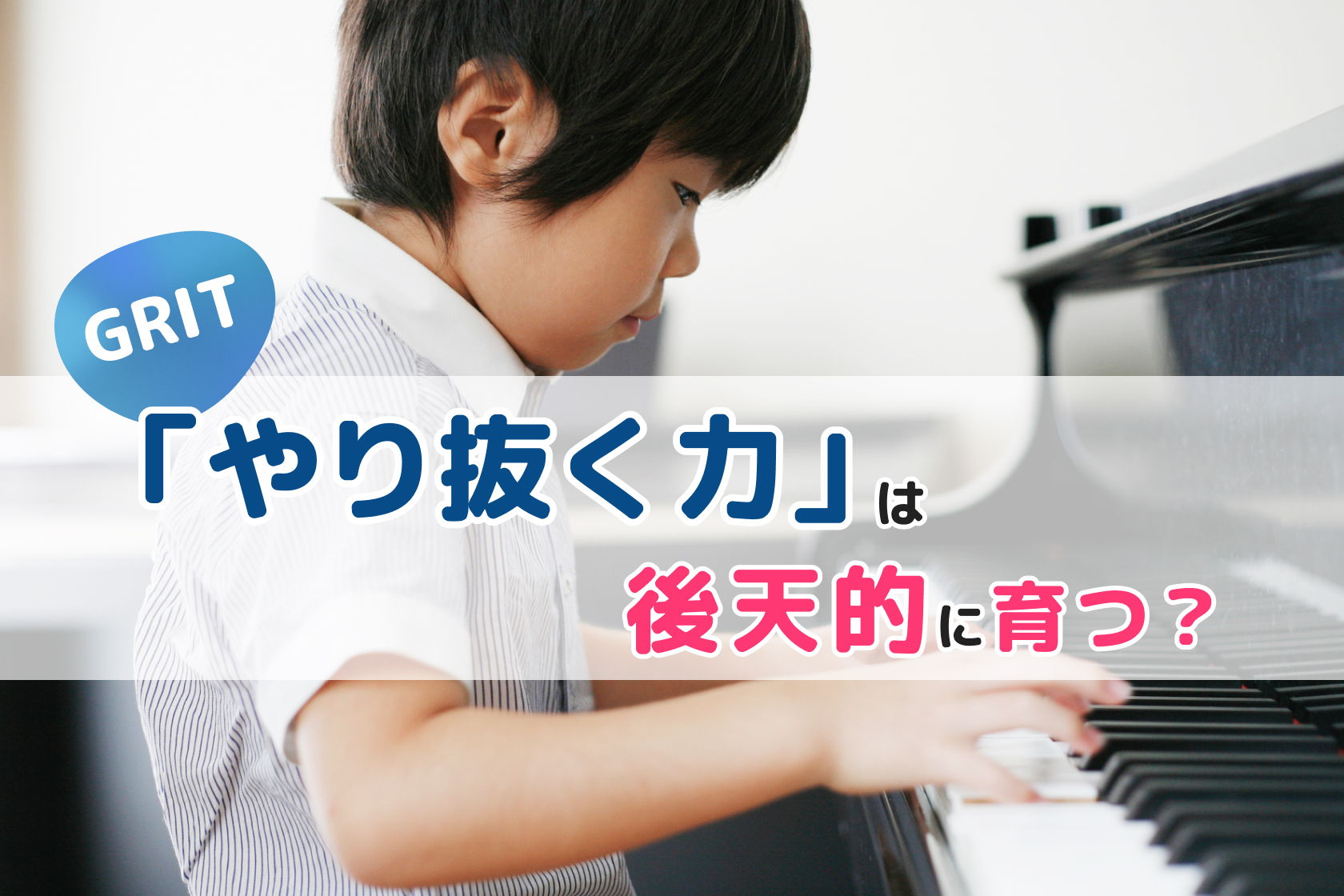
「GRIT(グリット)」という言葉を耳にする機会が増えました。
日本語では「やり抜く力」と訳されるこの概念は、目標に向かって粘り強く努力を続ける力を意味します。教育の現場やビジネスシーンでも、このGRITの重要性が注目され、学力やIQとは異なる「非認知能力」の一つとして取り上げられています。
実際、米国の心理学者アンジェラ・ダックワース氏は、著書『やり抜く力 GRIT』の中で、成功者に共通するのは「才能」ではなく「情熱」と「粘り強さ」、すなわち「GRIT(やり抜く力)」だと述べています。
では、このGRITは先天的に生まれ持った資質なのでしょうか?それとも教育や環境によって後天的に育てられるものなのでしょうか?
本記事では、GRITが先天的な資質なのか、それとも後天的に育つ力なのかを明らかにしながら、GRITと非認知能力との関係や、教育現場での実践的なアプローチについてもご紹介します。
INDEX
GRITとは何か|「才能」ではなく「継続」がカギ

GRITは、2つの要素から成り立っています。
- 情熱(Passion):自分の興味や価値観に基づいた目標を長期的に持ち続ける力
- 粘り強さ(Perseverance):困難があっても投げ出さずに継続する力
これらを総合した「やり抜く力」は、学力テストの点数では測れません。しかし、人生の成功や社会での活躍を予測するうえで極めて重要な要素です

GRITは後天的に育つ?非認知能力との関係

結論から言えば、GRITは後天的に育てることができます。事実、近年の研究や教育実践では、GRITを構成する「粘り強さ」や「自制心」「達成への意欲」などは、教育的働きかけによって伸ばせることがわかってきています。
IQや知識といった「認知能力」に対して、「非認知能力」とは感情や意欲、対人関係など、テストでは測れない力を指します。非認知能力は以下のような要素を含みます。
- 自己管理能力
- 主体性
- 協働力
- 探究心
- 自己肯定感
- 問題解決力
- 批判的思考力
- コミュニケーション力 など
GRITはこれらのうち、とくに「自己管理能力」「主体性」「探究心」と深く関連しており、まさに非認知能力の中核に位置するといえます。
科学的根拠|GRITと学力・社会性の関係
横浜市教育委員会の調査研究によると、GRITの高い児童は学力やソーシャルスキルの成長率が高い傾向にあると報告されています。特に「努力や成長が大事にされている学級(熟達目標構造)」では、GRITが高まりやすく、学習の楽しさや意味理解も促進されるという結果が出ています。
また、幼児を対象とした岐阜大学の杉浦氏らが行った研究でも、「忍耐力(GRITの主要要素)」が認知能力(知能指数)と有意な正の相関を持つことが明らかになっています。つまり、GRITは学力の土台にもなり得る非認知的資質なのです。
GRITを育てる教育的アプローチ

文部科学省は新学習指導要領の中で、子どもが主体的・対話的に学ぶ姿勢を重視しています。これはGRITの育成とも一致する方向性です。
ここでは、GRITを育むために教育現場や家庭で実践できる4つの具体的なアプローチをご紹介します。いずれも今日から取り組める内容ばかりですので、ぜひ参考にしてください。
1. 失敗を許容する文化づくり
失敗を恐れず挑戦できる環境は、GRITの土壌となります。失敗を「学びのチャンス」としてとらえ、そこから立ち直る経験が粘り強さを育みます。
2. 長期目標をもたせる
子ども自身が「何のために勉強するのか」「なぜ努力するのか」を考えることが、情熱を持続させる基盤になります。教師や保護者は、子どもの関心や価値観に寄り添った目標設定をサポートしましょう。
3. 自己効力感を高める声かけ
「あなたならできるよ」「前よりも上達してるね」など、小さな成功体験を言語化してフィードバックすることが、GRITの継続を支えます。
4. ルーティンや計画を立てる習慣
自分で計画を立て、それを管理しながら継続する力は、GRITの「自己管理力」と直結しています。たとえば「毎日10分読書」など、無理のない習慣化を促すとよいでしょう。
おわりに|GRITは才能ではなく、習慣と環境で育つ

GRIT(やり抜く力)は、生まれつきの才能ではなく、日々の教育や家庭での関わり方、適切な環境によって後天的に育てることができる非認知能力です。特に子どもの行動習慣や心の持ち方に働きかけることで、「粘り強く続ける力」や「目標に向かう情熱」は大きく伸びていきます。
「やり抜く力」を育てることは、テストの点数を上げるだけではありません。自分の人生を自分で切り拓いていくための土台を築くことなのです。これからの社会を見据え、GRITという非認知能力に目を向け、子どもたちとともにその力を育てていきましょう。
参考文献:
- アンジェラ・ダックワース(2016)『やり抜く力 GRIT』ダイヤモンド社
- 横浜市教育委員会「認知・非認知能力調査研究 報告書概要版(2023年)」
- 杉浦ひなのほか(2021)『幼児の認知能力と非認知特性の関連
- 一般財団法人日本生涯学習総合研究所『非認知能力の概念に関する考察<集約版>(2022年)』



