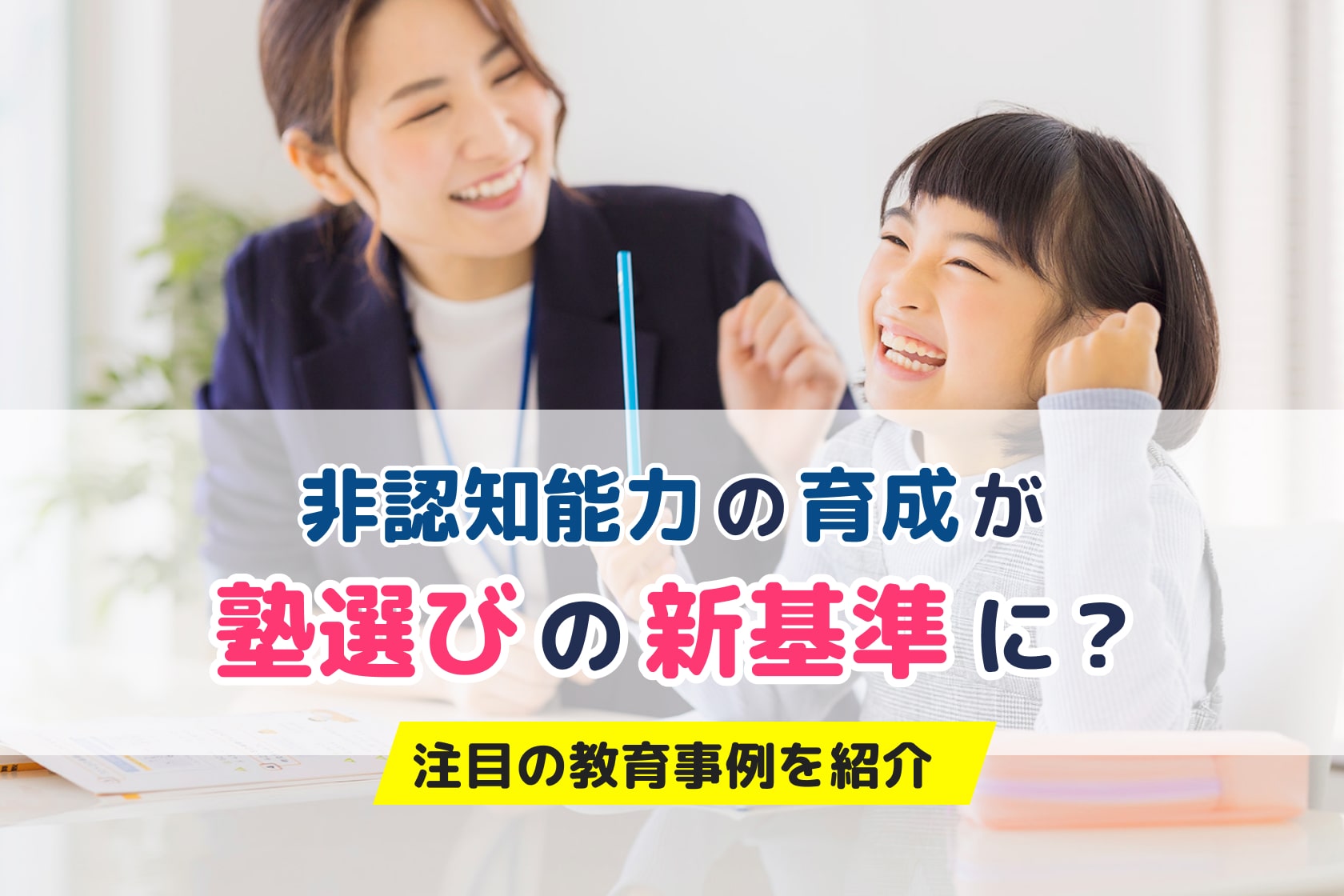
これまでの塾選びといえば「偏差値アップ」「志望校合格実績」が基準でした。
しかし、社会や大学入試の仕組みが変化し、将来的に求められる力も多様化している今、「非認知能力をどのように育むことができるか」が新しい塾選びの基準として注目され始めています。
本記事では、「非認知能力とは何か」「なぜ今、塾選びの新基準になりつつあるのか」、さらに「塾での具体的な取り組み事例」についてご紹介します。
INDEX
非認知能力とは?学力テストでは測れない“生きる力”
「非認知能力」とは、学力テストで点数化しやすい「認知能力」に対して、忍耐力・自制心・意欲・協調性などを指します。
- 認知能力:学力テストや模試で数値化できる知識量や論理力。
- 非認知能力:自己肯定感、粘り強さ、社会性など、人間性や生きる力。
ノーベル経済学賞を受賞したジェームズ・ヘックマンの研究でも、非認知能力が将来の学業成績や収入に強い影響を与えることが明らかになっています。つまり、学力だけでなく「どう生きるか」を支える力でもあるのです。

正解のない時代を生きる子どもたちに、
いま本当に必要な力とは?
非認知能力と学力の関係

「勉強に必要なのは学力だけ」と思われがちですが、実は非認知能力と学力には深い関係があります。
横浜市教育委員会が2023年に行った調査では、「メタ認知力(自分の学びを振り返る力)」「探究心」「やり抜く力」など非認知能力が高い子ほど、翌年の学力テストの結果も高いことがわかっています。
さらに岐阜大学などの研究では、幼児期に「忍耐力」が高い子どもは認知能力も高い傾向にあることが示されました。忍耐力は学力を支える土台になるのです。
つまり、非認知能力を育てることが学力向上にもつながるのです。
なぜ今、塾選びで非認知能力が重視されるのか?

1. 教育改革の流れ
大学入試改革や新しい学習指導要領では、知識の暗記だけでなく「思考力」「表現力」「協働性」が評価対象になっています。塾もこうした変化に対応する必要があり、非認知能力への注目が高まっています。
2. 保護者のニーズの変化
グローバル化やAIの進展により、単なる知識だけでなく、人と協力する力や自分を信じて挑戦する力といった「人間力」がますます求められるようになっています。こうした背景から、多くの保護者は学力偏重教育に不安を抱き、自己肯定感や協調性といった点数に表れない力も重視する傾向が強まっています。
3. 塾業界での差別化
運営者の視点でも、非認知能力を育てる取り組みは差別化ポイントになっています。保護者から選ばれる塾は、学力だけでなく「子どもの人間的な成長」にも目を向けているのです。
塾の非認知能力育成への取り組み事例
では、実際に非認知能力育成に力を入れている塾の例を見てみましょう。
花まる学習会(首都圏中心)
算数脳トレや作文教育を通じて「思考力」「やり抜く力」を養うユニークな塾。子どもが遊び感覚で算数パズルや文章発表に挑戦するスタイルは、自信・集中力・コミュニケーション力を大きく伸ばします。
参考:花まる学習会
Z会グループ(通信・教室展開あり)
進学指導のイメージが強いZ会ですが、近年は「探究学習プログラム(調べるひろがる探究講座)」を開設。通信添削教材とオンライン百科事典を活用し、「課題設定力」や「情報収集力」「分析・表現力」を段階的に学べます。子どもは自ら問いを立てて調べる姿勢や、考えを伝える力を自然に身につけることができます。
参考:調べるひろがる探究講座 3・4・5・6年生 - Z会の通信教育 小学生
浜学園(関西圏)
灘中学校合格実績日本一の「浜学園」では、「非認知スキル教育プログラム(SDGsカリキュラム)」を提供。「正解がない問題」に取り組むことで、非認知能力を鍛えて、新しい受験問題への対応力も磨きます。
参考:WEBSTAR SDGsカリキュラム|浜学園Webスクール
非認知能力育成が進学・将来に与える影響とは?
非認知能力の育成は、進学や将来に大きな影響を与えます。
たとえば大学入試においては、総合型選抜や推薦入試で「主体性」「協調性」「課題解決力」が重視されるため、非認知能力を育む取り組みは、そのまま入試での強みとなり得ます。さらに就職活動では、かつてのように偏差値や学歴だけでなく、「人柄」や「挑戦意欲」といった資質が評価される傾向が強まっています。
そして社会に出てからは、失敗から立ち直れる力こそが人生を切り拓く武器となり、長期的なキャリア形成や人生設計に直結していくのです。
まとめ:これからの塾選びは「学力」+「非認知能力」

これまで「偏差値至上主義」と思われがちだった日本の塾も、確実に「人間力も育む教育」へとシフトしつつあります。
非認知能力は学力テストでは測れませんが、子どもの未来にとって「一生ものの財産」となる力です。
保護者が塾を選ぶときには、志望校合格実績だけでなく、非認知能力の育成にも注力しているかが、これからの新しい基準となっていくでしょう。
参照・引用元
- 横浜市教育委員会「認知・非認知能力調査研究 報告書概要版」(2023年)
- 一般財団法人 日本生涯学習総合研究所「非認知能力の概念に関する考察<集約版>」(2022年)
- 岐阜大学ほか「幼児の認知能力と非認知特性の関連」(2021年)
- 花まる学習会
- 調べるひろがる探究講座 3・4・5・6年生 - Z会の通信教育 小学生
- WEBSTAR SDGsカリキュラム|浜学園Webスクール



