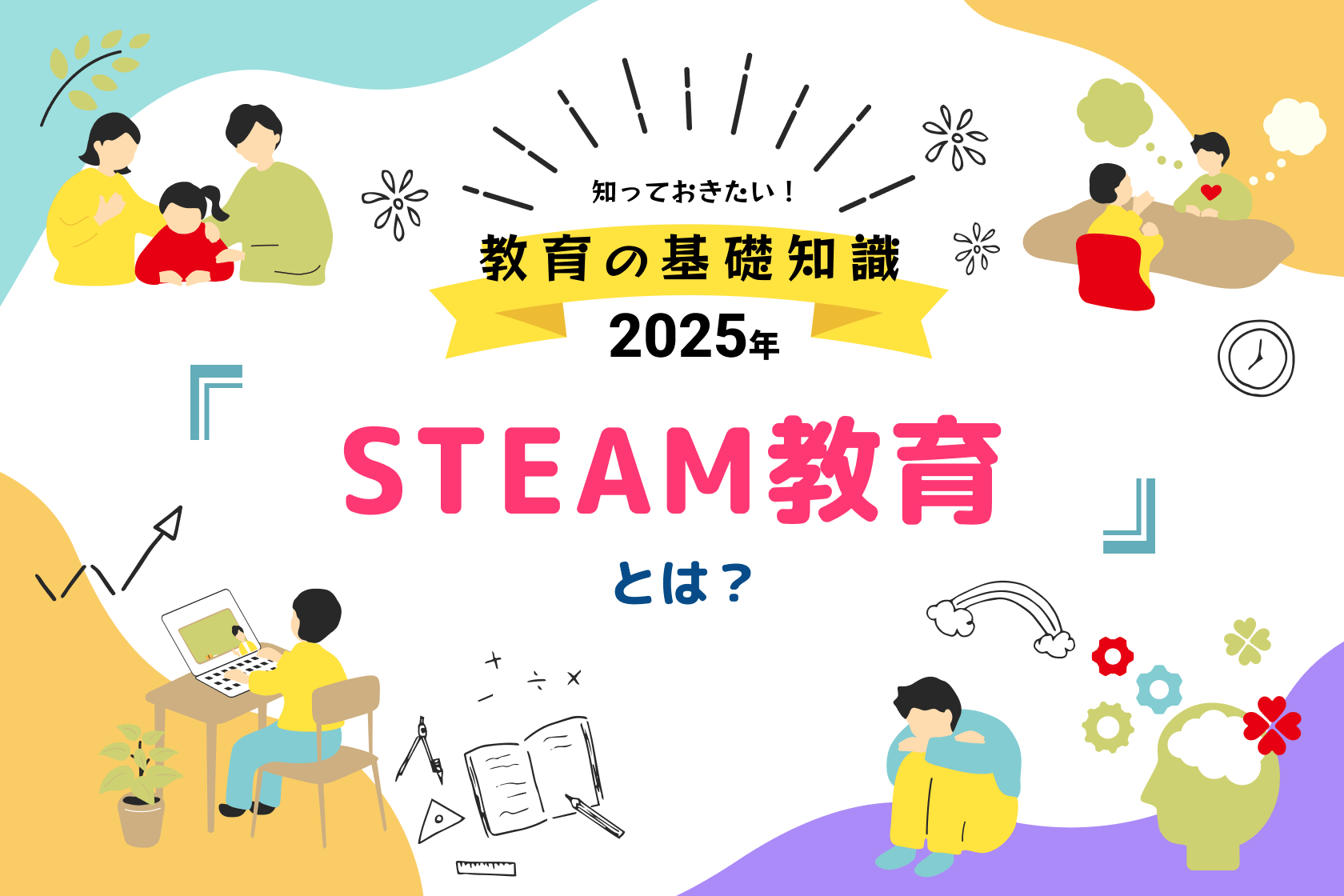
INDEX
はじめに|STEAM教育が注目される背景

近年の教育現場では「STEAM教育(スティーム教育)」という言葉を耳にする機会が増えています。これは、科学(Science)、技術(Technology)、工学(Engineering)、芸術(Art)、数学(Mathematics)を統合的に学ぶ教育のことを指します。AIの進化や予測困難な「VUCA時代(ブーカ時代)※」において、従来の知識詰め込み型教育だけでは不十分であると考えられるようになりました。
日本でも文部科学省が学習指導要領の改訂を通じて「探究学習」や「情報教育」を推進しており、STEAM教育はその流れの中で大きな注目を浴びています。また、非認知能力(協働力・主体性・探究心など)を育てる教育との親和性が高い点も特徴です。
本記事ではSTEAM教育の概念から、STEAM教育がなぜ必要とされているのか、また日本でのSTEAM教育の取り組みについて網羅的に解説します。
※VUCA時代とは
変化が激しく(Volatility)、先が読めず(Uncertainty)、複雑で(Complexity)、答えが一つに定まらない(Ambiguity)現代社会を指す言葉。

STEAM教育の基本概念
STEAM教育(スティーム教育)とは、以下の5つの分野を横断的かつ統合的に学ぶ教育アプローチです。
1. Science(科学)
科学的な思考力や論理的に物事を捉える力を育成。自然現象を理解するだけでなく、問題発見の姿勢を養います。
2. Technology(技術)
ICTやプログラミング教育と直結。技術を「使う」だけでなく「応用する力」を重視します。
3. Engineering(工学)
課題解決に向けて設計・検証・改善を繰り返す実践的な力。失敗を恐れず挑戦する経験が、GRIT(やり抜く力)にもつながります。
4. Art(芸術・リベラルアーツ)
STEAM教育の大きな特徴がこの「A」です。感性や創造性を重視し、デザイン思考や表現力を養います。科学や技術と組み合わせることで、新しい価値を生み出します。
5. Mathematics(数学)
数量的な思考や論理の基盤を提供。AIやデータ分析時代に不可欠なリテラシーです。
これらを、それぞれ独立して学ぶのではなく、課題解決やプロジェクト学習を通じて複数の分野を融合し学習するのが特徴です。
文部科学省も次のように述べて、STEAM教育の学習を推進しています。
文部科学省では、STEAMの各分野が複雑に関係する現代社会に生きる市民、新たな価値を創造し社会の創り手となる人材として必要な資質・能力の育成に向け、各教科等での学習を実社会での問題発見・解決に生かしていくための教科等横断的な学習を推進しています。
参照元:STEAM教育等の教科等横断的な学習:文部科学省
なぜ今、STEAM教育が必要なのか?

1. 社会の急速な変化
AIやロボットが急速に普及し、単純作業は自動化されています。その一方で、創造的に考え、他者と協力して課題を解決する力が人間に求められるようになっています。
2. 非認知能力との関係
STEAM教育は「知識」だけではなく、協働力・主体性・探究心といった非認知能力を伸ばすのに効果的です。研究でも、メタ認知や知的好奇心の高い子どもほど学力が伸びる傾向が示されています。

正解のない時代を生きる子どもたちに、
いま本当に必要な力とは?
3. 国際的な教育動向
OECD(経済協力開発機構)の「Education 2030」プロジェクトやPISA調査(OECD, 2018)では、知識の活用力や社会情動的スキルの重要性が強調されています。STEAM教育はその潮流に合致しており、国際競争力を高めるためにも不可欠です。
STEAM教育のメリット
STEAM教育には、子どもたちの学びや将来に直結する多くの利点があります。ここでは、その代表的なメリットを4つに整理して紹介します。
- 学びの主体性を育む
自ら問いを立て、探究し、答えを導くプロセスを重視。受け身の学習から主体的な学びへとシフトします。 - 失敗を恐れないマインド形成
工学的アプローチやプロジェクト学習を通じて「トライ&エラー」を経験。忍耐力や挑戦する姿勢が育まれます。 - 学力と非認知能力の両立
知識の獲得だけでなく、創造力・協働力・自己管理能力などの非認知スキルが自然と鍛えられます。 - 将来のキャリア形成に直結
DX・AI人材不足が叫ばれる中、STEAM教育で培った力はそのまま就職・キャリア形成に結びつきます。
日本でのSTEAM教育の取り組み

日本でも、社会の変化に対応できる人材を育てるために、学校教育から民間教育まで幅広い場面でSTEAM教育の導入が進んでいます。
学校教育
プログラミング教育必修化や総合的な探究の時間において導入が進んでいます。高校では2022年度から新科目「情報Ⅰ」が必修となり、データ活用やAI基礎を学ぶようになりました。
民間教育・塾
プログラミング教室や探究型学習塾が広がりつつあります。STEAM教育を売りにする学童も登場し、子どもの非認知能力育成にも力を入れています。
まとめ|STEAM教育が育む未来の力
STEAM教育は、理数系とアートを組み合わせた枠組みにとどまらず、知識・思考・感性・協働を一体的に育む新しい学びの形です。文部科学省が推進する探究学習やICT活用とも深く結びつき、これからの教育の基盤になるといえるでしょう。
これからの時代に求められるのは、テストで測れる学力(認知能力)だけでなく、創造力や人間性を含めた「生きる力(非認知能力)」です。STEAM教育は、子どもたちが将来社会で自立し、他者と協力しながら新しい価値を創造するための力を育み、その重要性は今後ますます高まっていくでしょう。
参考・引用元
- 横浜市教育委員会委託調査「認知・非認知能力調査研究」報告書概要版(2023年)
- 一般財団法人 日本生涯学習総合研究所「非認知能力の概念に関する考察<集約版>」(2022年)
- 杉浦ひなのほか「幼児の認知能力と非認知特性の関連」(2021年)
- OECD「The Future of Education and Skills: Education 2030」(2018)
- STEAM教育等の教科等横断的な学習:文部科学省



