
INDEX
はじめに|なぜ今「メタ認知」が注目されるのか
近年、教育現場や学習科学の分野で「メタ認知」という言葉を耳にする機会が増えています。メタ認知とは、自分の認知活動を客観的に把握し、適切にコントロールする力のことです。言い換えれば「自分がどのように考えているのかを理解し、その過程を調整できる力」です。
文部科学省が掲げる新しい教育の方向性においても、学力や認知能力と並んで「学びを自律的に進める力」として重要視されており、今後の教育に欠かせない要素といえます。
本記事では、メタ認知の定義や役割、学力との関係、非認知能力とのつながり、そして学校や家庭で育む方法について分かりやすく解説します。
メタ認知とは?その定義

メタ認知は、大きく次の2つの要素で構成されます。
- メタ認知的知識
自分の認知特性や課題の性質、学習方略についての知識。
例:「自分は英単語を覚えるのが苦手」「図を使うと理解が進む」 - メタ認知的活動(技能)
学習の計画、モニタリング、評価といった調整のプロセス。
例:「この問題は難しいから時間配分を変えよう」「解き方が合っているか確認しよう」
この2つを組み合わせることで、学習者は「効率的に学ぶ力」を高めることができます。
メタ認知と学力の関係
横浜市教育委員会と横浜国立大学の共同研究(2023年)では、児童生徒のメタ認知と学力の関係を調査しました。その結果、メタ認知が高い子どもは1年後の学力テストの成績も高い傾向にあることが示されました。
ただし関連は「強いものではない」とされています。つまり、メタ認知だけで学力が決まるわけではなく、知的好奇心や粘り強さ(グリット)、授業の楽しさなど複合的な要因が学力向上に結びついていると考えられます。
メタ認知と非認知能力のつながり
メタ認知は、非認知能力(自己制御力、やり抜く力、協働性など)とも深く関わっています。
- 自己制御力:感情や行動を調整する力は、メタ認知的制御と密接に関係。
- やり抜く力(GRIT):困難に直面したとき「自分の努力の仕方」を振り返り、改善する力が不可欠。
- 協働性:他者との学び合いを通じて、自分の思考を客観視する力が高まる。
このように、メタ認知は非認知能力を支える「ハブ」のような存在であり、子どもの総合的な成長に影響を及ぼします。
非認知能力について詳しくは、下記のページを参照してください。
学校教育におけるメタ認知の育成

メタ認知は意識的に育てることが可能です。学校教育では、次のような取り組みが効果的です。
1. 学習計画を立てる
授業の冒頭に「今日の学習目標」を児童自身に書かせる。終わりに「できたこと・できなかったこと」を振り返る。
2. 振り返りジャーナル
ノートに「今日の勉強で難しかったところ」「工夫したこと」を記録し、学習方法を客観視する。
3. ペア学習での説明
友達に解き方を説明することで、自分の理解の浅い部分に気づく。
4. 教師の声かけ
「どうしてそう考えたの?」「別の方法もあるかな?」と問いかけ、思考を言語化させる。
家庭でできるメタ認知を育む工夫

家庭でも日常生活を通じてメタ認知を伸ばすことができます。
- 声かけの工夫:「どうやって考えたの?」「次はどんな方法を試す?」
- 選択肢を提示:「宿題を先にする?遊びを先にする?」と計画を立てさせる。
- 失敗を肯定:「なぜ失敗したかを考えれば、次はもっと上手にできるね。」
こうした習慣が「学びを自分でコントロールする感覚」を育てます。
Q&A|メタ認知に関するよくある質問
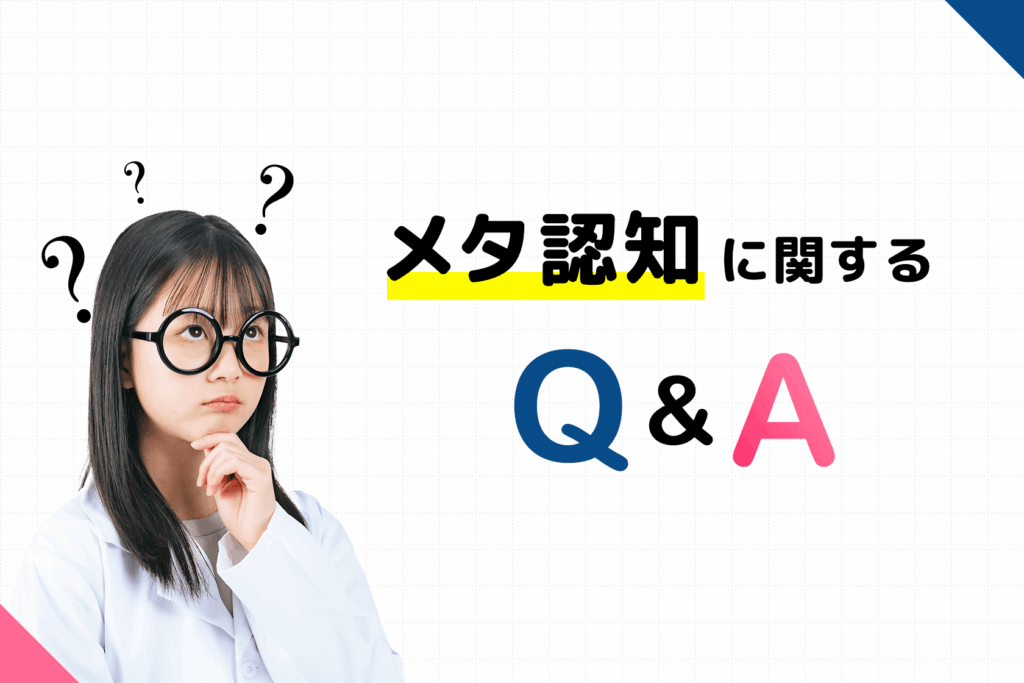
Q1. メタ認知は生まれつきの能力ですか?
A. いいえ、メタ認知は後天的に伸ばせる能力です。幼少期から少しずつ発達し、教育や経験によって誰でも高められます。
Q2. メタ認知が低いと学力は伸びませんか?
A. 直結するわけではありませんが、研究では一定の関連が示されています。むしろ、メタ認知を育てることで「効率的な学び方」を獲得でき、長期的に学力を支えます。
Q3. どんな方法でメタ認知を鍛えられますか?
A. 振り返り・記録・他者との対話が有効です。特に「なぜそうしたのか」を確認する習慣が大切です。
まとめ|未来を生き抜く力としてのメタ認知

メタ認知は「自分の学びを客観的に理解し、調整する力」であり、学力だけでなく非認知能力を支える基盤となる重要なスキルです。
これからの教育では、知識の多さよりも「その知識をどう活かし、自ら学びを深めていけるか」が問われます。その中心にあるのがメタ認知です。子どもがこの力を身につけることで、学力の向上はもちろん、未来に挑戦する力や可能性を大きく広げていくことができるでしょう。
参考文献・出典
- 横浜市教育委員会・横浜国立大学 (2023)「認知・非認知能力調査研究 報告書概要版」
- OECD (2018) The Future of Education and Skills 2030
- 文部科学省 (2017, 2019) 学習指導要領



