
INDEX
はじめに:なぜ「失敗」は恐れるべきことではないのか?

子育てをしていると、わが子が何かでつまずいたり、失敗したりするのを見るのは胸が痛むものです。「失敗させたくない」という思いから、つい先回りしたり、口出ししたりしてしまう親御さんも多いのではないでしょうか。
しかし、子どもの成長において、「失敗」は避けるべきものではなく、「最高の学び」へと変えることのできる貴重な機会です。特に近年、学力や偏差値といった「認知能力」と並び、「非認知能力」が子どもの将来の成功に不可欠な要素として注目されています。
本記事では、非認知能力という視点から、子どもの失敗をどのように捉え、親としてどのように関わることが、子どもの未来を切り開く力になるのかを詳しく解説します。
非認知能力とは何か?「失敗」と非認知能力の関係
非認知能力の定義と重要性
非認知能力とは、学力テストなどで数値化しにくい、「意欲」「協調性」「自制心」「やり抜く力(グリット)」「問題解決能力」「好奇心」といった、心の持ち方や対人スキルや態度など、生きていく上で非常に重要な力です。
これに対し、認知能力は、学力やIQなど数値で測れる能力を指します。
ハーバード大学の経済学者ジェームズ・ヘックマン氏の研究などにより、非認知能力の高さが、学歴、所得、健康、幸福度といった人生のあらゆる側面に大きな影響を与えることが示され、その重要性が注目を集めています。
失敗こそが非認知能力を育む「土壌」
では、この非認知能力と「失敗」は、どのように関係するのでしょうか。
子どもが何かを「失敗」するとき、それは「目標に向かって行動した証拠」です。そして、失敗から立ち直るプロセスこそが、非認知能力を鍛える絶好の機会となります。
- 「もう一度やってみよう」と立ち向かう姿勢は、やり抜く力(グリット)を育みます。
- 失敗の原因を自分で考え、次はどうするかを導き出す行為は、問題解決能力を養います。
- 失敗した時の悔しい気持ちや、次に成功した時の喜びを感じる経験は、自己肯定感や感情調整能力を高めます。
親が失敗を恐れ、子どもから挑戦の機会を奪ってしまうと、これらの非認知能力が育つ「土壌」を奪ってしまうことになりかねません。
「失敗」を最高の学びに変える!親が持つべき3つの非認知能力視点

親が子どもの失敗を「最高の学び」に変えるためには、親自身が非認知能力的な視点を持ち、関わり方を変える必要があります。
視点1:結果ではなくプロセスを承認する(自己効力感の育成)
子どもがテストで点数が悪かった、試合で負けてしまった、友達と喧嘩した。親はつい「なんで失敗したの?」「次はもっと頑張りなさい」と結果や原因に言及しがちです。しかし、この瞬間、子どもが本当に必要としているのは「結果にかかわらず、自分の努力が認められること」です。
- NGな声かけ:「どうしてこんな簡単なミスをしたの?」「勝てなかったのは練習不足よ」
- OKな声かけ:「最後まで諦めずに頑張ったの、お母さんは見ていたよ」「悔しい気持ちになったのは、それだけ真剣だった証拠だね」
ポイント
結果が良い時だけ褒めるのではなく、目標に向かって努力した過程、挑戦した勇気、諦めずに粘った姿勢など、非認知能力につながる行動を具体的に承認しましょう。これにより、子どもは「自分はできる」という自己効力感を高め、失敗を恐れず再挑戦できるようになります。
視点2:「Why?」ではなく「How?」で原因を考えさせる(問題解決能力の育成)
失敗の原因を問う時、親は感情的になって「なぜ、また同じことをしたの!」と「Why(なぜ)?」で問い詰めてしまいがちです。しかし、「なぜ?」は子どもを責めているように聞こえやすく、言い訳や隠ぺいにつながりやすい問いかけです。
失敗を学びに変えるためには、「How(どうする)?」という未来志向の問いかけで、自分で解決策を考えさせる機会を与えることが重要です。
- NGな声かけ:「なんで、友達のものを壊しちゃったの?」「どうしていつも忘れ物をするの?」
- OKな声かけ:「次は同じことが起こらないように、どうすればいいかな?」「どうやったら、忘れ物を防げるか一緒に作戦を立ててみようか」
ポイント
失敗を過去の出来事として責めるのではなく、未来の成功のためのデータとして捉え直させましょう。自分で解決策を見つけ出す経験が、主体性と問題解決能力という強力な非認知能力を育みます。
視点3:親自身が「失敗しても大丈夫」というモデルを示す(レジリエンスの育成)
子どもは、親の姿を映す鏡です。親がちょっとした失敗(料理を焦がす、物をなくす、仕事でミスをするなど)をした時、どのように振る舞っているかを見て、失敗への態度を学びます。
親が自分の失敗を隠したり、過度に落ち込んだりしていると、「失敗は悪いこと」というメッセージを子どもに伝えてしまいます。
- NGな行動:自分のミスをごまかす、子どもに「内緒ね」と言う、ミスに対して自分を責め続ける
- OKな行動:「あら、焦がしちゃった!でも大丈夫、この失敗から次は火加減を調整するね」「仕事でこういうミスをしちゃったんだ。でも、すぐに謝って、どうすれば次は防げるか考えたよ」と失敗をオープンにする
ポイント
親が失敗してもすぐに立ち直り(レジリエンス)、それを次に活かす前向きな姿勢を見せることで、子どもは「失敗してもやり直せる」「失敗は成長のきっかけになる」と自然に学びます。親の「失敗しても大丈夫」という態度は、子どもに安心感と挑戦意欲を与えます。
Q&A:子どもの失敗と非認知能力について親が抱く疑問
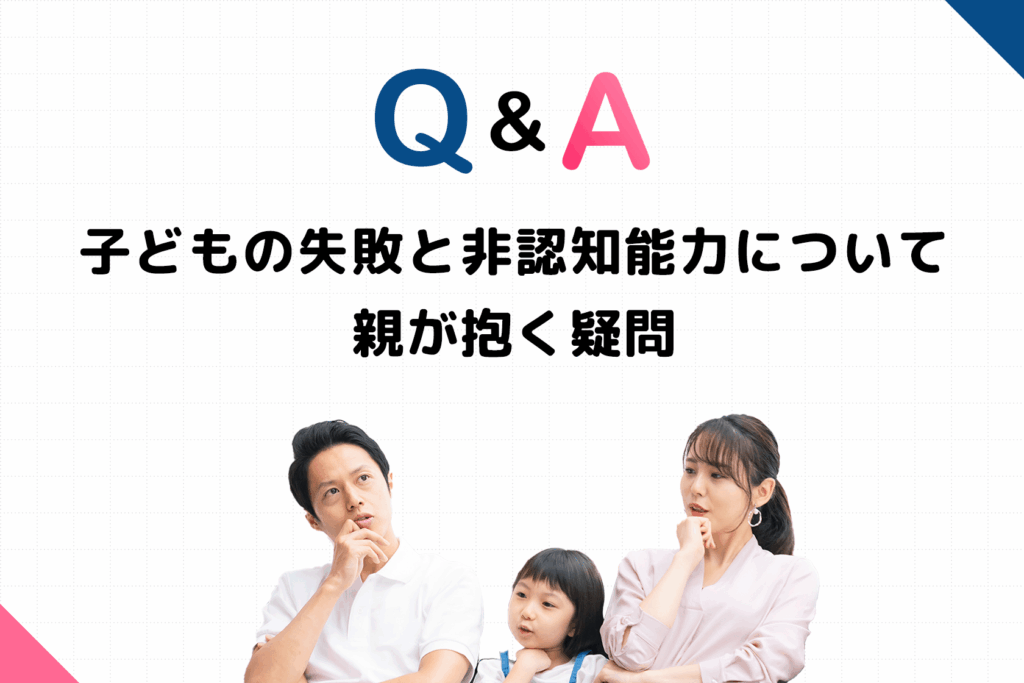
失敗を経験させることが大事なのは分かりますが、怪我やトラウマになるような大きな失敗は避けたいです。どこまで親が手出しせず見守るべきでしょうか?
重要なのは、「安全と命に関わる失敗」と「心理的な成長につながる失敗」を区別することです。
- 安全に関わること(例:交通ルール違反、危険な場所での遊び):これは親が介入し、明確なルールと境界線を教えましょう。
- 成長につながる失敗(例:友達との喧嘩、テストの点数、練習試合での負け、忘れ物):「失敗しても、親が助けてくれる・話を聞いてくれる」という心理的な安全基地を確保した上で、できるだけ自分で乗り越えさせる機会を与えましょう。
親がすべて解決するのではなく、失敗した子どもの感情をまず受け止めた後、「次にどうするかは、自分で決めてごらん」と、「考える機会」を渡すことが、自律性を育みます。
失敗した時に、子どもが「もうやらない」と諦めてしまった場合、親はどう声をかけるべきでしょうか?
A: 子どもが諦めるのは、失敗からくる「無力感」や「自己否定感」が原因であることが多いです。この時、親が「頑張れ!」と精神論で励ますのは逆効果になりがちです。
まずは、「休んでもいいよ」「諦める気持ち、わかるよ」と、子どもの感情に寄り添い、安心感を与えましょう。
その上で、「じゃあ、この前はどこまでできたかな?」「前に頑張ってできたところは、どんなところ?」と、過去の「成功体験(できたこと)」や「努力の過程」に焦点を当てて思い出させてください。
そして、「前よりほんの少しだけ簡単なところから、もう一度やってみない?」と、スモールステップで再挑戦を促します。非認知能力であるやり抜く力(グリット)は、この「小さな成功体験の積み重ね」によって鍛えられます。
まとめ:親の「まなざし」が子どもの未来を拓く

子どもの失敗に直面した時、親の反応は、子どもの非認知能力の成長を大きく左右します。
「失敗=悪いこと」という認知から、「失敗=挑戦の証、成長のチャンス」という非認知能力的な視点に切り替えることが、親の最も重要な役割です。
子どもの努力と挑戦を心から承認し、「どうする?」という未来志向の問いかけで背中を押すこと。親自身が失敗を恐れない姿を見せること。
親の温かく、かつ前向きな「まなざし」が、子どもの非認知能力という一生ものの財産を育み、未来を力強く切り拓く原動力となるでしょう。
参考文献
- ジェームズ・J・ヘックマン(2015) 『幼児教育の経済学』東洋経済新報社
- 中山芳一(2020)『家庭、学校、職場で生かせる!自分と相手の非認知能力を伸ばすコツ』東京書籍
- アンジェラ・ダックワース(2016)『やり抜く力 GRIT』ダイヤモンド社



