
INDEX
はじめに:学力テストで測れない「力」をどう捉えるか
学力テストの点数や偏差値では見えない「非認知能力」。
それは、意欲・協調性・忍耐力・自己肯定感・コミュニケーション力・感情のコントロール力など、人生を豊かに生きるための“心の力”です。
OECD(経済協力開発機構)はこれを「社会情動的スキル」と定義し、学習経験を通して発達し、社会経済的成果に長く影響を与える能力としています。
しかし、非認知能力は学力テストの点のように単純に数値化できません。
そこで注目されているのが、「見える化」というアプローチです。
子どもの日常の姿や行動の中から、非認知能力を“観察・記録・共有”することで、成長の方向性を具体的に把握し、支援につなげることができます。
非認知能力の“見える化”が注目される理由
1. 教育現場での評価の多様化
文部科学省が提唱する「資質・能力の三つの柱」では、「知識及び技能」「思考力・判断力・表現力」と同時に「学びに向かう力・人間性」も重視されています。
これは、非認知能力を意識した教育への転換を意味します。
特に2017年以降、探究学習や協働学習が増える中で、「自分の考えを伝える」「他者と協力する」といった力が求められるようになりました。
これらはすべて非認知的側面であり、見えにくいながらも成長に欠かせない要素です。
2. 保護者が子どもの「変化」を捉えにくい
学力のように点数で見えないため、家庭では「できる・できない」で判断しがちです。
しかし実際には、失敗しても再挑戦する姿勢や友達への思いやりなど、日常の中に非認知能力の伸びが隠れています。
この小さな成長を可視化できれば、子どもの自己肯定感を高め、より良いサポートが可能になります。
非認知能力を見える化する3つの方法

① 行動観察によるチェック
最も基本的で効果的なのが、「観察」による見える化です。
教師や保護者が日常の行動・発言・反応を意識して観察し、記録することで、成長の兆しが見えてきます。
観察のポイント例
| 観察項目 | チェックポイント |
| 意欲・主体性 | 新しいことに挑戦しようとする姿があるか |
| 粘り強さ | 失敗してもあきらめず取り組むか |
| 協調性 | 友達の意見を聞いて行動できるか |
| 自己制御 | 感情的になった時に落ち着こうとするか |
| 共感性 | 他者の気持ちを理解しようとする姿があるか |
※一度の観察ではなく、長期的な変化を見ていくことが重要です。
② チェックリストによる自己・他者評価
教育現場や家庭で注目され始めているのが、チェックリスト形式の見える化ツールです。
「非認知能力検定※」や研究機関等が開発したリストでは、具体的な質問に○×や5段階で回答することで、子どもの特性を可視化できます。
チェックリスト例(抜粋)
- 目標を立てて行動することができる
- 最後までやり遂げようとする気持ちがある
- 困っている友達を助けようとする
- 自分の意見を落ち着いて伝えられる
- 相手の気持ちを考えて行動できる
こうした質問を通して、「どの能力が育っていて、どの力を伸ばしたいか」が明確になります。
※「非認知能力検定」では、チェックリストの回答だけではなく、少人数での体験型活動の行動観察も組み合わせることにより、非認知的な要素を総合的に評価します。
③ ポートフォリオ・振り返りノートの活用
学習過程や日常の行動を記録して振り返ることも、非認知能力を見える化する有効な方法です。
たとえば、
- 学校の活動記録(探究ノートや学習日誌)
- 家庭での週末チャレンジ(「できたことノート」など)
- 保護者と子どもの振り返り会話
を続けることで、「どんなときにがんばれたか」「どう感情をコントロールできたか」といった内面的な成長を言語化できます。
記録を見返すことは、子どもの「自分はできる」という自己効力感を育てる効果もあります。
保護者ができる“見える化”サポートのコツ

- できたことを言葉で伝える
→「最後までがんばれたね」「優しい声かけできたね」と具体的に褒める。 - 失敗を“成長の種”として扱う
→「うまくいかなかったけど、挑戦できたことがすごい」と視点を変える。 - 定期的に振り返りをする
→「1ヶ月前より○○ができるようになったね」と変化を一緒に確認する。
非認知能力の“見える化”とは、単に評価することではなく、成長のプロセスを親子で共有することなのです。
Q&A|非認知能力の“見える化”に関するよくある質問
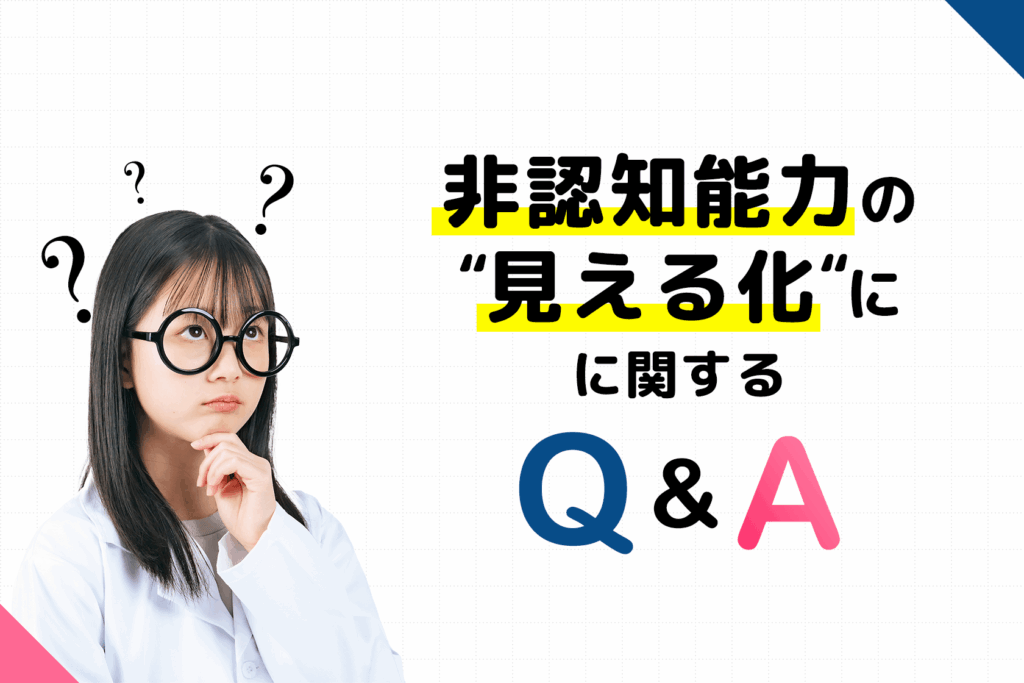
Q1. テストの点が高い子は、非認知能力も高いの?
A. 学力と非認知能力にはゆるやかな関連があります。研究では、知的好奇心や粘り強さ、メタ認知が高い子どもほど、学力テストの成績も高い傾向が確認されています。ただし強い相関ではなく、学力だけで非認知能力の高さを判断することはできません。
Q2. 非認知能力を伸ばすにはどうすればいい?
A.「結果よりプロセスを認める」ことが大切です。
失敗を責めるのではなく、「次はどうしたらうまくいくかな?」と一緒に考えることで、自己効力感が育ちます。
Q3. 子どもの成長を数値化することに抵抗があります…
A. 見える化は“評価”ではなく、“理解”のための手段です。
数値は目安として捉え、対話や観察を通じてその子らしい成長をサポートしましょう。
まとめ|非認知能力の“見える化”は、子どもの「心を育てる」第一歩
非認知能力を見える化することは、「子どもの今」を正しく理解し、未来を伸ばすことにつながります。
チェックリストや観察記録を通して、 “変化のストーリー”を見つめていきましょう。
教育現場でも家庭でも、非認知能力の育成は「気づく力」から始まります。
今日からできる小さな観察と声かけが、子どもの大きな成長を支えるはずです。
参考文献
- 文部科学省(2020)『新しい学習指導要領のポイント』
- 文部科学省(2020)『学習指導要領改訂に関する広報資料』
- 横浜市教育委員会委託調査「認知・非認知能力調査研究」報告書概要版(2023年)
- 非認知能力検定公式サイト



