
INDEX
はじめに:なぜ今、「非認知能力」が成功の鍵なのか
「うちの子には将来、幸せに、そして力強く生きていってほしい」—これは全ての親御さんの願いでしょう。これまでは、学力や偏差値といった「認知能力」の高さが将来の成功に直結すると考えられてきました。
しかし、現代社会は変化が激しく、AI(人工知能)の進化により、知識を詰め込むだけの力では太刀打ちできない時代になりました。そこで世界的に注目されているのが、「非認知能力」です。
非認知能力とは、学力テストでは測れない、「目標に向かって頑張る力」「人とうまく関わる力」「感情をコントロールする力」といった、生きていく上で土台となる力の総称です。
ノーベル経済学賞受賞者のジェームズ・ヘックマン博士の研究をはじめ、多くの研究が、この非認知能力の高さこそが、学歴、キャリア、収入、さらには幸福度にまで、人生のあらゆる側面に影響を与えることを示しています。
本記事では、将来、困難に負けずに成功を掴む子どもたちが共通して持っている非認知能力に裏打ちされた5つの特徴を、具体的なエピソードを交えて解説します。
特徴1:失敗を恐れず、最後まで「やり抜く力」(グリット)を持っている

非認知能力が高い子どもたちの最も際立った特徴は、「粘り強さ」や「やり抜く力(GRIT)」を持っていることです。
「失敗=終わり」ではなく「失敗=データ」
非認知能力が高い子は、失敗は落ち込む要因ではなく、「次はどうすればいいか」という新しいデータと考えます。目標達成までの道のりには、つまずきや壁がつきものだと理解しており、一時的な失敗で心が折れることはありません。
具体的な行動
- 難しいパズルやブロックを、完成するまで何時間でも集中して取り組む。
- 苦手な課題でも、自分なりの工夫(例:時間を区切る、好きな道具を使う)をして継続する。
- 友達との遊びでうまくいかなくても、原因を自分で分析し、次の交渉で別の提案を試みる。
家庭でできるサポート
結果ではなく、「諦めずに挑戦したプロセス」や「粘り強く頑張った時間」を承認してあげましょう。「できたからすごい」ではなく、「最後までよく頑張ったね」という声かけが、グリットを育みます。
特徴2:自分の気持ちを理解し、適切に表現・調整できる(感情をうまくコントロールする力)
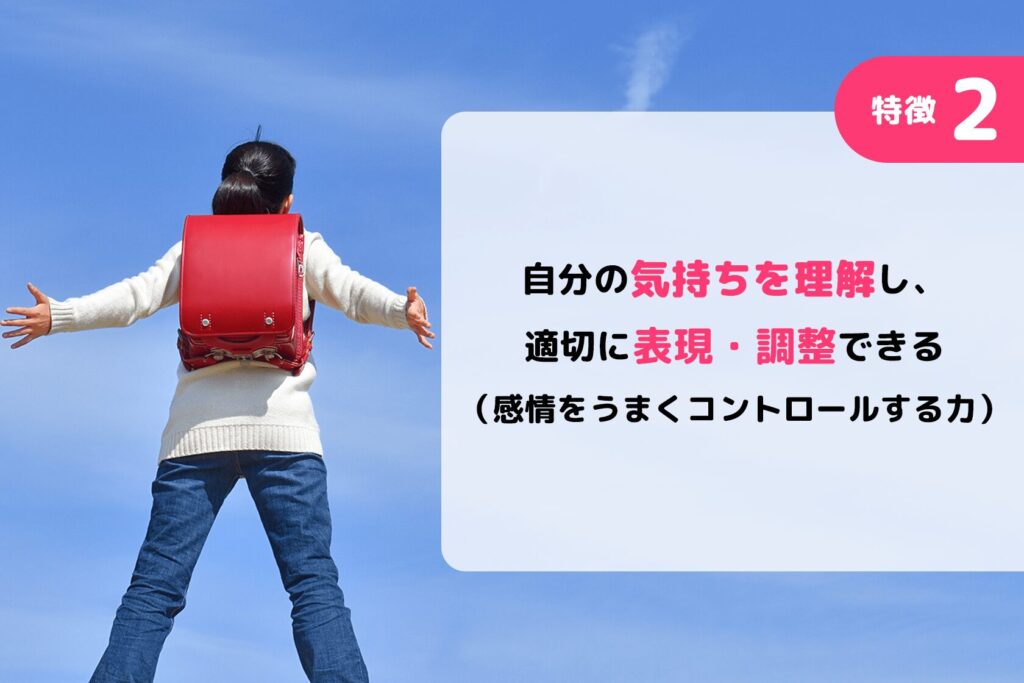
感情の波をうまく乗りこなす感情の調整力も、非認知能力の高さを示す重要なサインです。
非認知能力の高い子どもは、自分の感情(喜び、怒り、悲しみ、不安)に気づき、それをその場にふさわしい形で表現したり、我慢したりすることができます。
衝動的な行動に「待った」をかけられる
欲しいものが手に入らない、友達に意地悪をされた—このような時、反射的に泣いたり、怒鳴ったりするのではなく、「今、自分は悲しいんだな」「少しイライラしている」と一歩引いて状況を認識できます。
この「一歩引く」ことができるため、衝動的な行動(例:友達を叩く、すぐに諦めて物を投げる)に走ることが少なく、冷静に状況に対処し、問題解決に移行することができます。
具体的な行動
- 怒りを感じた時、すぐに手を出すのではなく、深呼吸をしたり、その場を離れたりしてクールダウンできる。
- 自分の番を待つ時、イライラしてもルールや約束を理解して静かに待てる。
- 嬉しいことがあった時、喜びを言葉で伝え、周りの人とも分かち合える。
家庭でできるサポート
感情を否定せず、「今、悔しい気持ちなんだね」「悲しかったんだね」と、まずは子どもの感情を代弁・共感してあげることが大切です。その後に、「どうしたらその気持ちを落ち着かせられるかな?」と一緒に方法を考えることで、感情の対処法を学ぶことができます。
特徴3:自分で問いを立て、積極的に情報を取りに行く(好奇心・探究心)
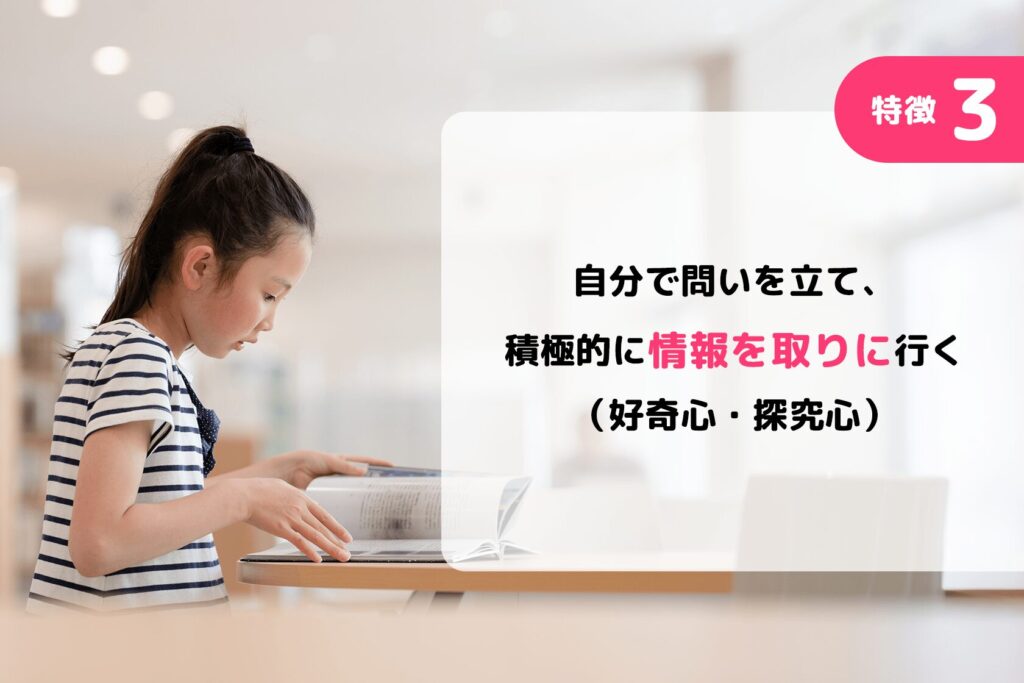
将来、社会で活躍する子どもたちは、与えられた知識を受け身で学ぶだけでなく、「なぜ?」「どうして?」という飽くなき好奇心と探究心を持っています。これも、非認知能力の大きな特徴です。
知識を「点」で終わらせず「線」につなげる力
彼らは、日常生活の中で気になることを見つけると、それを深く掘り下げようとします。図鑑で調べたり、親に質問攻めにしたり、自ら実験を試みたりと、主体的に行動することで、知識を自分の経験と結びつけます。
この探究心は、将来的に「創造性」や「イノベーションを生み出す力」に直結します。
具体的な行動
- 興味を持ったことについて、図書館で関連書籍を何冊も借りてくる。
- 遊びの中で、「これとこれを混ぜたらどうなるだろう?」と予測を立てて実験してみる。
- 疑問に感じたことを、親や先生に臆せず質問し、納得いくまで考える。
家庭でできるサポート
子どもが発する「なぜ?」を面倒がらず、一緒に考える姿勢を見せましょう。答えを教えるだけでなく、「〇〇はどう思う?」「どこを見たらわかるかな?」と、情報を取りに行く方法を促す声かけが、探究心を育てます。
特徴4:他者の立場で物事を考え、協力できる(協調性・社会性)
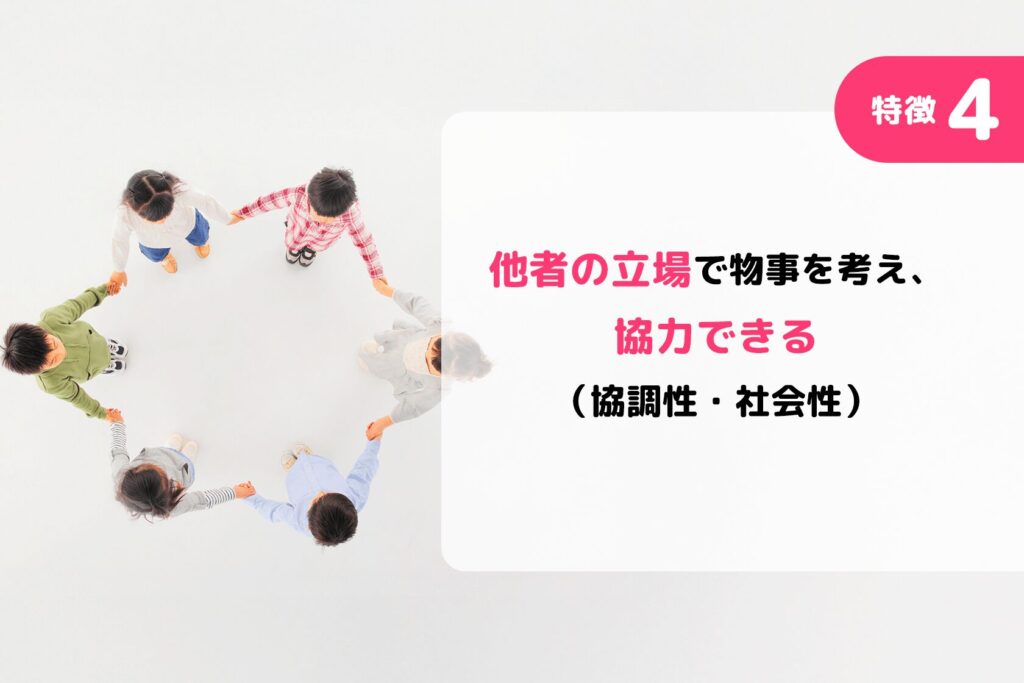
非認知能力が高い子どもたちは、「自分と他者は違う存在である」ことを理解し、多様性を受け入れ、協働することができます。これは「協調性」や「社会性」と呼ばれる力です。
Win-Winの関係を築くコミュニケーション力
集団生活の中では、意見の衝突やトラブルは避けられません。非認知能力の高い子は、自分の意見を主張する力だけでなく、相手の気持ちを推し量る「共感力」を持っています。
そのため、一方的に自分の意見を押し通すのではなく、「どうすればお互いが気持ちよくいられるか」という視点で物事を考え、妥協点や最適な解決策を見つけ出すことができます。
具体的な行動
- 友達が困っている時、自分から声をかけ、手助けできる。
- 遊びの中で、ルール変更が必要になった時、多数決ではなく、全員の意見を聞いてより良いルールを提案できる。
- 友達が失敗した時、責めるのではなく、励ます言葉をかけられる。
家庭でできるサポート
「もし〇〇ちゃんの立場だったら、どんな気持ちになると思う?」といった視点を変える問いかけを日常的に行いましょう。また、家族内でも、親が子どもの意見を尊重し、話し合いで解決策を見つけ出す協働のモデルを示すことが効果的です。
特徴5:自分の長所を理解し、自分を信じる力がある(自己肯定感・自己効力感)

すべての非認知能力の土台となるのが、「自己肯定感」と「自己効力感」です。
自己肯定感とは「自分は自分のままで価値がある」と感じる力、自己効力感とは「自分ならできる、目標を達成できる」と信じる力です。
挑戦を可能にする「心のエンジン」
非認知能力が高い子どもは、これらの力が強いため、新しい挑戦を恐れず、失敗しても「次こそはできる」と自分を信じることができます。これは、親から与えられた過度な自信ではなく、「自分の力で乗り越えた経験」によって培われた確固たる自信です。
具体的な行動
- 発表やスピーチなどで、緊張しても自信を持って自分の意見を伝えられる。
- 自分の苦手な部分も認めつつ、得意なことを伸ばそうと努力する。
- 失敗した時、他人のせいにせず、「次はどうしよう」と前向きに考える。
家庭でできるサポート
結果ではなく、存在そのものを肯定する言葉をかけ続けましょう。「生まれてきてくれてありがとう」「あなたがいてくれて幸せよ」といった、無条件の愛情を示すことが土台になります。そして、子どもが「自分で決めて、自分でやり遂げた」という成功体験を積めるよう、見守る機会を提供しましょう。
まとめ
非認知能力が高い子どもは、やり抜く力(グリット)や感情のコントロール、探究心、協調性、自己肯定感といった「生きる力」を兼ね備えています。これらは学力や将来の成功、幸福感を支える土台になります。
家庭では、結果ではなく努力の過程を認め、感情に共感し、挑戦を励ます声かけが効果的です。こうした日常の積み重ねが、子どもの「自分を信じて挑戦する力」を育み、将来の自立と成功を支える原動力になるでしょう。
参考文献
- ジェームズ・J・ヘックマン(2015)『幼児教育の経済学』東洋経済新報社
- アンジェラ・ダックワース(2016)『やり抜く力 GRIT』ダイヤモンド社
- 中山芳一(2020)『家庭、学校、職場で生かせる!自分と相手の非認知能力を伸ばすコツ』東京書籍
- ダニエル・ゴールマン(1996)『Emotional Intelligence(EQ〜こころの知能指数)』講談社



